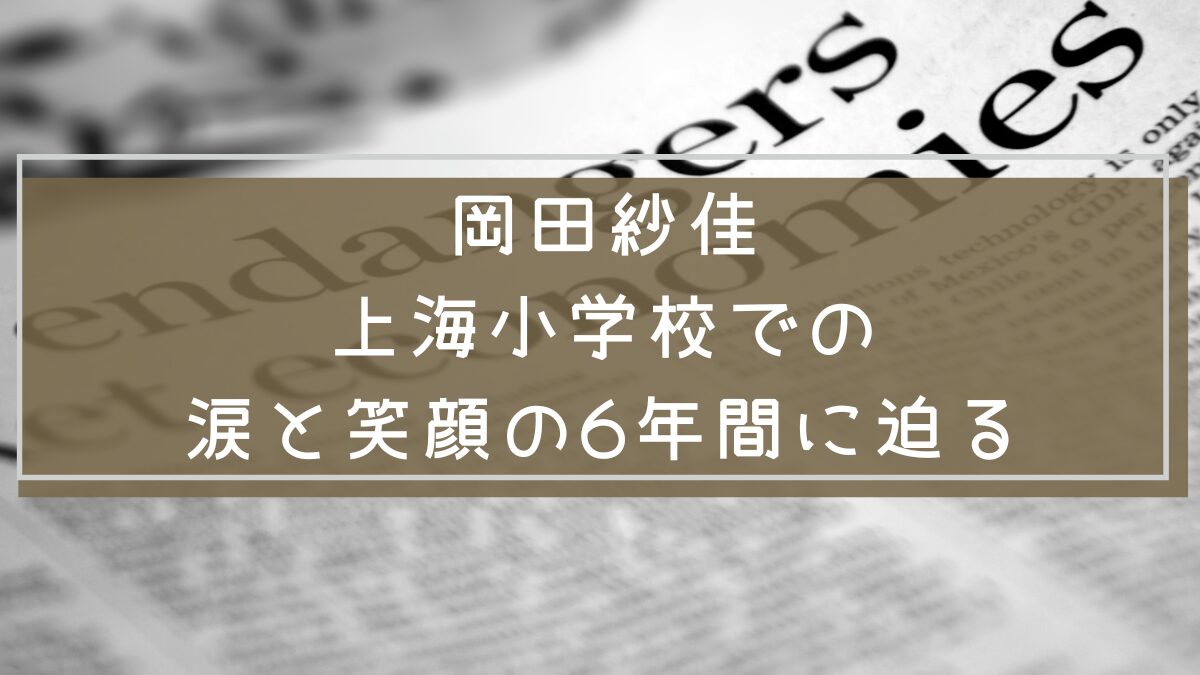「中国と日本、どっちが本当の自分の場所なんだろう?」
このように考えたことがあるハーフの方は、意外と多いんじゃないでしょうか。
この記事では、岡田さんの子ども時代から日本に戻ったあとのカルチャーショック、そしてハーフとしての苦悩と成長までを、本人のエピソードをもとにリアルにたどります。
ハーフって何だろう、人と人が分かり合うってどういうこと?
そんな気持ちにふと触れてみたくなる内容になっています。
生い立ちと家族背景
- 本名:岡田 紗佳(おかだ さやか)
- ニックネーム:紗佳、おかぴー
- 生年月日:1994年2月19日(現在 31歳)
- 出身地:東京都世田谷区
- 血液型:O型
- 身長・スリーサイズ:170 cm、B85 cm/W58 cm/H83 cm、Gカップ、靴24.5 cm
- 所属事務所:アーティストハウス・ピラミッド
- モデル活動:2011年に第43回non‑noモデルオーディションでグランプリ&クリニーク賞を受賞し、2012年2月号から『non‑no』専属モデルとして活動
- タレント活動:『ZIP』や『ネプ&イモトの世界番付』などに出演
- プロ雀士としての活動:2017年に日本プロ麻雀連盟に入会しプロ雀士としてデビュー
岡田紗佳さんは、日本人の父と中国人の母のもとに生まれました。
日本で誕生し、国籍も日本ですが、そのルーツは二つの国にまたがっているんですよね。
日本での生活が13年間、中国での暮らしが6年間という経歴を持ち、どちらの文化にも深く触れてきた方です。
そのため、幼少期から異なる言語や価値観が混ざり合う環境に自然と身を置くことになりました。
家族の中でも、父からは日本的な礼儀や考え方を、母からは中国ならではの食文化や家庭の温かさを学んだそうです。
日本と中国を行き来した幼少期の環境
岡田さんは6歳から12歳まで上海で暮らし、それ以前とその後は日本で生活してきました。
日本の幼稚園から一転、中国の小学校という環境に飛び込みました。
季節ごとに違う行事や学校の雰囲気に慣れるまで、時間がかかったかもしれません。
ただ、その中で培った「順応力」は、今の彼女の活動にも大きく影響しているはずです。
日本に帰国してからも、中国での経験があるからこそ、周囲との視点の違いに気づきやすくなった…そんな部分もあったのかもしれません。
 ryomo
ryomo小学生からいきなり中国で生活というのは不安だらけだったでしょうね!
上海で暮らした6年間


岡田紗佳さんが6歳から12歳まで過ごした上海での日々は、人生の土台をつくる大切な時間だったはずです。
日本とは全く違う街並みや、人の距離感に最初は戸惑いながらも、日々の暮らしの中でたくさんの温もりに触れていったのでしょうね。
その期間はただの留学や一時滞在ではなく、まさに“生活”として根を下ろした6年間だったと言えるでしょう。
おばあちゃんとの二人暮らし
上海での暮らしは、お母さんの母にあたるおばあちゃんとの二人きりから始まりました。
親元を離れる寂しさはあったはずですが、おばあちゃんの穏やかな声や、毎朝の温かいご飯が安心感をくれたそうです。
日本語と中国語が飛び交う日常は、不思議と居心地がよくなっていったでしょうね。
買い物や市場へのお出かけも二人で。
ときには値切り交渉のやり方まで教えてもらいながら、生活の知恵を吸収していったそうです。



おばあちゃんと暮らしていると温かい性格になるイメージがありますね!
日本文化に触れられる団地での生活
住んでいたのは、近所づきあいが盛んな団地。
そこには日本語教師が2人いて、さらに
「もののけ姫みよー!!」
と毎日のように話しかけてくる日本人の男の子もいました。
親日家が多く、日本の話題が日常に混ざる環境だったため、日本文化から切り離されることはなかったそうです。
団地の人々と食卓を囲んだり、日本のアニメや映画を一緒に観たりして、国境を感じさせない関係が築かれていました。
「セーラームーンみたい」と慕われた日々
団地の住人たちは岡田さんを
「セーラームーンみたい!」
と可愛がってくれました。
髪や顔立ちが少し珍しかったこともあり、まるで身近なヒーローのように接してくれたそうです。
大人も子どもも隔てなく声をかけてくれる環境で、岡田さんは人との距離を恐れない性格を少しずつ育んでいったことでしょう。
現地小学校での学びと日常


岡田紗佳さんは上海滞在中、外国人向けではなく地元の小学校に通っていました。
そこは日本とはまるで違う学習スタイルで、日々の空気感もかなり緊張感があったそうです。
けれど、厳しさの中にも友達との笑顔や、子どもらしいやり取りがちゃんとあったそうです。
厳しい授業と膨大な勉強時間
通った学校は
「すっっっっっっっごく厳しい」
と岡田さんが言うほど。
朝から夕方まで授業が詰まり、宿題も山のように出されていました。
放課後になっても机に向かい続ける日々で、遊びの時間はほとんど取れなかったそうです。
それでも、同じように頑張る友達の存在があったからこそ、なんとかやり切れたんでしょうね。



日本の学校はそこまで宿題が山盛りというイメージはないので中国のほうが教育に力をいれているのかもしれませんね。
歴史の授業で感じた複雑な思い
歴史の授業で日本と中国の戦争について学ぶ時間は、岡田さんにとって一番つらい瞬間でした。
普段は仲良くしてくれる友達も、この時ばかりは視線や言葉が変わってしまうことがあったそうです。
「なんでそういうときだけ日本を嫌うのかな」
と、子どもながらに疑問と悲しさが混ざった感情を抱えていたようです。
授業が終わった後も、その空気を引きずることがあったでしょうね。
友人関係に影を落とした国籍意識
友達とケンカをしたときや先生に叱られたとき、「日本人」と呼ばれることが増えました。
普段は「日本に連れてって!」と笑って話してくれるのに、負の感情が向いた瞬間に国籍が武器のように使われてしまう。
そんな経験が、岡田さんの中で人との距離の取り方に小さな影を落としたのかもしれません。
それでも笑い合える時間があったから、完全には人を嫌いにならなかったんでしょうね。
日本に帰国してからのカルチャーショック


上海での6年間を終えて日本に戻った岡田紗佳さんは、懐かしさよりも戸惑いの方が大きかったそうです。
中国にいたときよりも、むしろ周囲の目が冷たく感じられる場面が増えてしまったとのこと。
文化や言葉はすぐに馴染めても、人の心にある壁はそう簡単に越えられなかったのでしょう。
中国滞在時より増えた偏見
驚くことに、日本に戻ってからの方が「中国人」という言葉を悪意と一緒に投げられることが多くなりました。
学校で仲間外れにされたり、すれ違いざまに心ない言葉を浴びせられたり。
「中国にいるときの方がまだ優しかったかもしれない」
と感じる瞬間もあったそうです。
偏見は遠くにあるものではなく、意外と身近に潜んでいるものなのかもしれません。



中国にいるときは「日本人」と言われ日本に戻れば「中国人」といわれる。いったいどれだけ傷ついてきたのか私には想像もつきません。
芸能活動に影響したアイデンティティの課題
芸能界入りを決めたとき、お父さんから「中国人のハーフって言って大丈夫なの?」と心配されたこともあったそうです。
ネット上には「好きだったけど、中国人って知って嫌いになった」という声も実際にあったそうです。
そういう言葉は、夢に向かう勢いを一瞬で鈍らせるものですよね。
それでも岡田さんは、隠すよりも受け止める道を選びました。
揺れるアイデンティティと向き合う覚悟は、この時期にさらに強まったのかもしれません。
ハーフとしての自分らしさ
岡田紗佳さんは、日本と中国という二つのルーツを持つ自分を、時に誇らしく、時に重く感じながら生きてきました。
その感情は常に一定ではなく、環境や人の言葉によって揺れ動いてきたんですよね。
けれど、その中で見えてきたのは「自分は自分」という揺らぎにくい芯だったのかもしれません。
「血筋」で決めつけられることへの違和感
生まれも育ちもほとんど日本なのに、「半分中国の血が入っている」というだけで色眼鏡で見られる。
もしこの半分がフランスやイギリスだったら、きっと違う反応だったんじゃないか…そんな考えが浮かんだこともあったそうです。
人は見た目や背景で判断されやすいけれど、それが本当に正しいのかは疑問なんですよね。
国籍や人種よりも「人」として向き合う大切さ
岡田さんは、中国人にもマナーが悪い人はいるけれど、日本にも同じような人はいると気づきました。
逆に、優しい心を持った人も国を問わずたくさんいる。
そう考えるようになってからは、「国籍」よりも「その人自身」を見ようという気持ちが強くなったそうです。
きっと、それは長い経験の中で自分に刻まれた一番大きな学びでしょうね。



岡田さんだからこそ本当の意味で感じることが出来たことなんだと思います。
中国への気持ちの変化と前向きな思い
偏見や差別を受けたことで、中国に対して嫌な感情を抱いた時期もあったそうです。
でも最近では、それも自分の一部だと素直に受け止められるようになったのだとか。
「こんなに近いんだから、もっと仲良くしたい」という前向きな気持ちも芽生えてきたとのこと。
ハーフとしての葛藤は、いつの間にか未来への希望に変わっていったのかもしれません。
まとめ
- 日本と中国、二つの文化の間で育った複雑な幼少期
- 上海での温かい出会いと厳しい学校生活
- 偏見や差別を経て見つけた自分らしさ
岡田紗佳さんの歩みは、文化や国境を越えて人と向き合う大切さを教えてくれました。
幼い頃に上海で暮らし、おばあちゃんとの時間や団地での仲間との交流が心の支えでした。
けれど、小学校では国籍を理由にした距離や誤解に悩む日も多かったそうです。
日本に戻ってからは、さらに偏見が増えて驚いた瞬間もあったでしょう。
それでも、経験を通して「国ではなく人を見る」視点を育み、中国への想いも前向きに変わっていきました。
どんな環境でも自分を受け入れる力こそ、今の彼女を支えているのかもしれません。
これからも岡田紗佳さんを応援していきたいと思います。