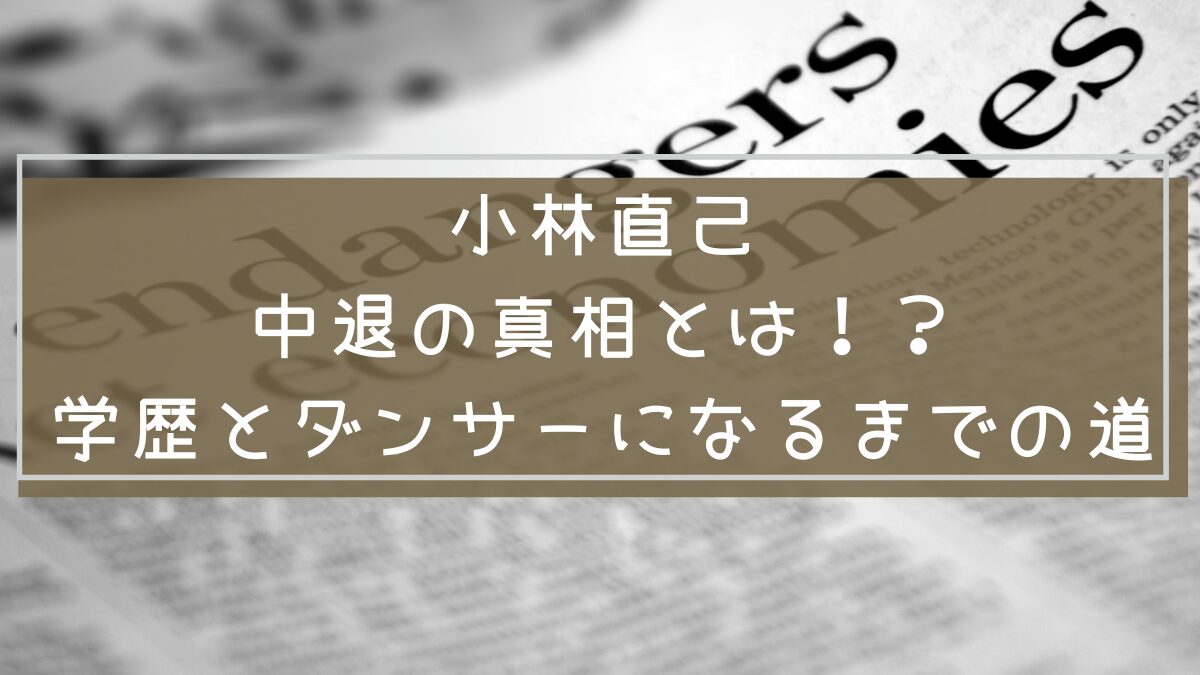ryomo
ryomo小林直己さんはどんな学生生活を送ってきたのでしょう?
「ダンサー」「俳優」「モデル」と多方面で活躍する小林直己さん。
その華やかなキャリアの裏にある“学歴”に注目が集まっているのをご存じでしょうか。
ただ有名校を卒業したという話ではなく、どんな環境で育ち、何を学び、どのように現在の表現力に結びついているのか。
その過程には、哲学との出会い、中退という決断、高校時代の葛藤や家族との関係など、深いエピソードが詰まっています。
この記事では、小林さんの学生時代から現在までの歩みをたどりながら、彼の内面や人間力の原点をひもといていきます。
学歴を“肩書き”ではなく“成長の軌跡”として見る視点を持てる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧くださいね。
プロフィールと現在の活躍から見る「学歴」の重要性
小林直己(こばやし なおき)プロフィール
- 生年月日:1984年11月10日
- 出身地:千葉県印西市
- 身長:187cm
- 血液型:O型
- 本名:同じ(旧芸名はNAOKI)
- 所属グループ:EXILE、三代目J SOUL BROTHERS(リーダー)
- 職業:ダンサー、俳優、モデル
ダンスや俳優業、さらには国際的な活動まで幅広く活躍する小林直己さん。
EXILEおよび三代目J SOUL BROTHERSのパフォーマーとして知られています。
長身で端正なビジュアルに加え、言葉の端々に感じられる知性や落ち着きも、ファンを惹きつける理由なのでしょうね。
だからこそ、「この人はどんな学びを経て、今のような深みを得たのか?」という学歴への関心が自然と高まるわけです。
単なる肩書きとしての学歴ではなく、思考や価値観のベースとなる“知の積み重ね”がどこにあるのか。
そのルーツをたどることで、小林さんの本質にもう一歩近づけるような感覚があるんですよね。
事実、小林さんは学生時代から真面目に学業に取り組み、勉強と表現の両方に向き合ってきた方です。
進学先や選択した学問分野も、彼の内面を映す大きなヒントになっているのは間違いありません。
そして、その姿勢が、発言一つひとつに説得力を持たせる理由でもあるのだと思います。
ダンサー・俳優・モデルとしての顔と学歴の関係性
世界を舞台に活躍する小林さんは、EXILEのパフォーマーという枠を超えて、映画やファッション業界でもその存在感を放っています。
『たたら侍』での映画出演や、パリコレクションへの参加といった活動の幅広さは、身体的な表現力だけでなく、精神的な奥行きのある人物であることを物語っています。
このような表現者としての厚みは、偶然生まれたものではありません。
高校や大学で培われた知的な土台が、彼の動きや言葉の一つひとつに深みを加えているのではないかと感じさせられます。
哲学的な問いを通じて思考の習慣が形成され、それがステージ上の一瞬の動作にも表れてくる。
感情を内に閉じ込めるのではなく、丁寧に掘り下げ、観客に向けて静かに伝えていくような印象があります。
また、小林さんはメディアでの受け答えにも独特の落ち着きがあり、言葉を選ぶ姿勢にも強い誠実さが見られますよね。
それはまさに、日々の学びと自己探求の積み重ねが生んだもの。
学歴そのものというより、そこを通じて得た「考える力」と「自分を見つめる目」が、あらゆる表現に生きているのだと思います。



内面を磨いてきた人の表現って、なぜか一瞬で心を持っていかれますよね!
幼少期の家庭環境と学びの原点
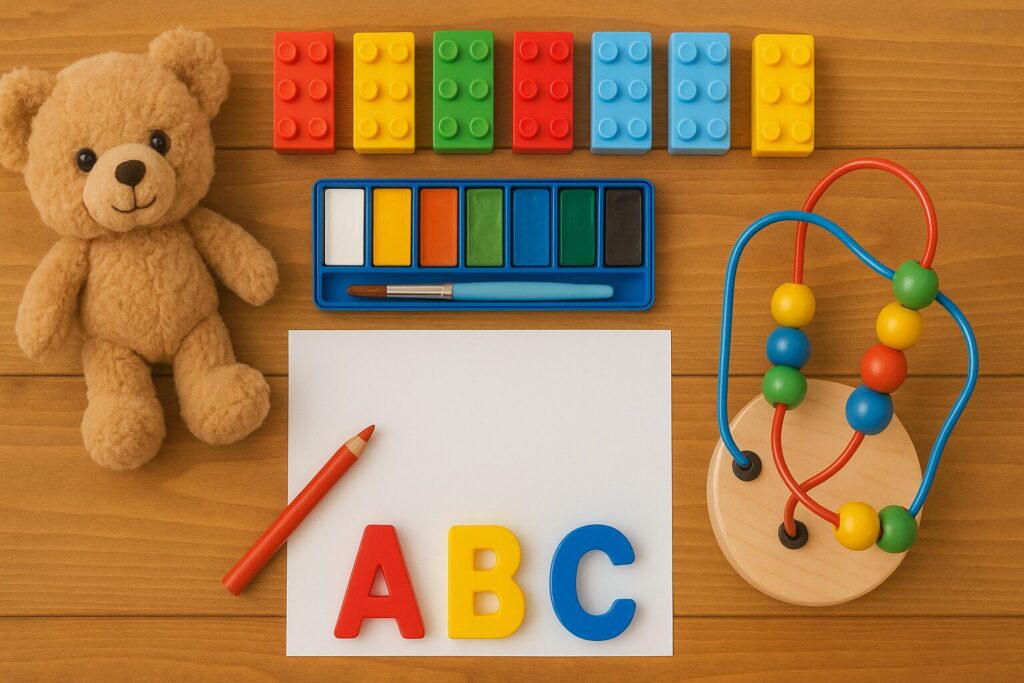
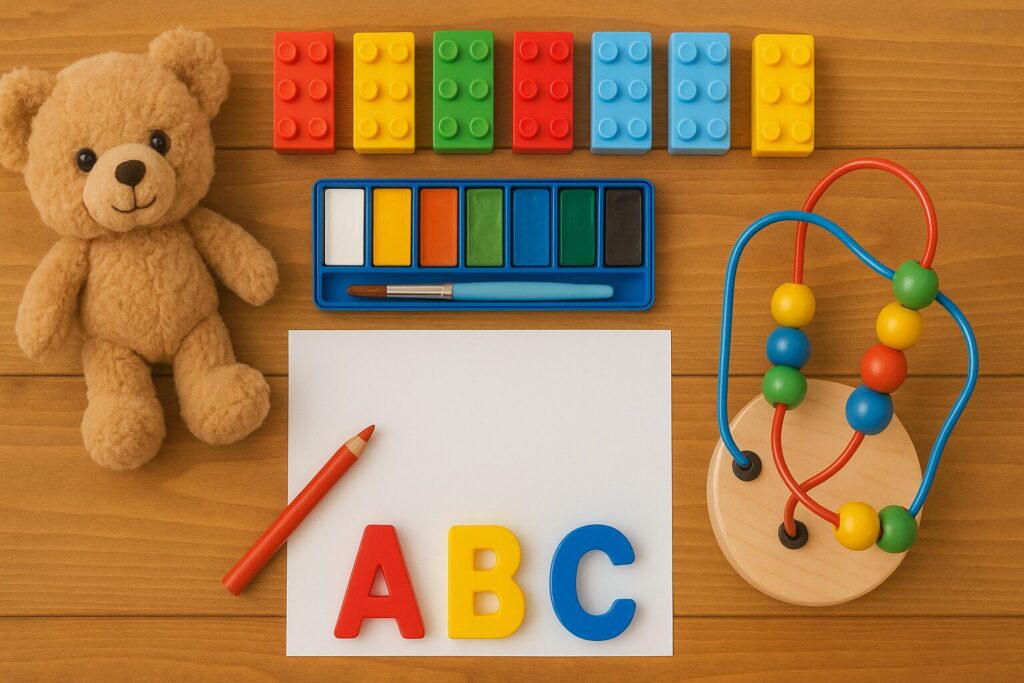
人の価値観や思考の原点には、幼少期の家庭環境が大きく関わっています。
小林直己さんも例外ではなく、5人兄弟の一人として育った日常の中に、後の知的好奇心や表現力の芽があったようです。
新聞を通して「読むこと」への関心が育まれた経験など、学びの始まりを感じさせるエピソードが詰まっています。
5人兄弟の4番目として育った小学生時代
小林直己さんの出身は千葉県印西市。
小学校は市内にある印西市立木刈小学校に通っていました。
この時期、小林さんは7人家族というにぎやかな家庭環境で育ちました。
兄が2人、姉が1人、そして弟が1人いる5人兄弟の4番目として、大家族の中で揉まれながら成長していったようです。
こうした家庭では、自然と上下の関係や協調性が身につくものですよね。
特に4番目という立場からは、兄や姉の姿を見て学ぶことも多かったのではないでしょうか。
また、自分のポジションを考えながら過ごす日々が、後にチームの中での役割や空気を読む力に繋がったように思えます。
さらに印象的なのは、母親が新聞配達の仕事をしていたという点。
家族ぐるみで新聞に触れる機会が多く、身近に情報や活字がある環境に小さい頃から自然と馴染んでいたようです。
日常の中にある「読むこと」「考えること」が、学びの種になっていたんですよね。
新聞との出会いと、記事の誤りを指摘したエピソード
小林さんがまだ小学生だった頃、新聞は単なる情報源ではなく、興味の対象そのものでした。
最初は4コマ漫画に夢中になっていたそうですが、徐々に活字の記事にも関心が向いていったようです。
特に将棋欄の記事を読んでいた際に、掲載されていた内容に明らかな間違いがあることに気づきます。
それを新聞社に自ら連絡して知らせたというエピソードがあるのですが、これには驚かされますよね。
大人でもなかなか躊躇してしまうような行動を、小学生の段階で自然に実行してしまう。
その姿勢に、すでに好奇心や責任感の強さ、そして論理的な思考力が表れていたのではないかと感じます。
このとき母親に褒められたことが、きっと大きな自信にもなったのでしょうね。
「間違いを見つけたら正す」という姿勢や、「疑問を持つ力」を肯定してもらえた経験は、小林さんにとって学びの原体験とも言える大切な記憶だったはずです。
そしてこの頃に培った「読む力」や「考える力」が、後に哲学という学問への関心につながっていく流れにも納得がいきます。
何気ない幼少期の出来事が、思考や表現の土台をつくっていたんでしょうね。
思春期を支えた中学時代の音楽との向き合い方
小林さんが通っていたのは、千葉県印西市にある公立校・木刈中学校。
この中学校には、のちに女優として活躍する真木よう子さんも在籍していたことがあり、地域内では比較的知られた存在かもしれません。
そんな環境の中で、小林さんは中学生らしい日常を送りながら、早くも人生の根本的なテーマと向き合うようになります。
「自分って何なんだろう」。そう考えたときに、不安やイライラで眠れない夜があったと語っており、感情の揺れに対して非常に敏感だったことがわかります。
それは、単なる思春期特有の揺らぎではなく、「自分自身と正面から向き合う力」を持っていたからこそ、感じ取れた感覚なのかもしれません。
誰もが通る成長の過程でありながら、多くの人はそこから目を逸らしてしまいがち。
小林さんの場合は、その不安から逃げるのではなく、むしろそれをきっかけにして自分を深く掘り下げていったように思えます。
そのとき支えになったのが、J-POPをはじめとする音楽の歌詞だったそうです。
言葉にできない感情を、誰かの歌が代弁してくれる。
そんな経験を重ねる中で、小林さんは音楽が心に与える力の大きさに気づいていきます。
合唱部で育まれた表現力と音楽の素養
中学時代、小林さんは合唱部に所属していました。
ここでの経験は、今の彼のパフォーマンスの根底を支えているといっても過言ではないでしょう。
特に合唱は、他者と音を重ねながら一つの世界をつくる繊細な芸術でもあります。
声の出し方、ハーモニーの感じ方、相手の呼吸を読み取る力。
そうした一つひとつが、小林さんの身体表現に通じる大切な素養になっていったのだと思います。
合唱部で過ごした時間は、単に音楽的な技術だけでなく、「他者と一緒に一つのものを創る」という協調性や集中力も育ててくれたはずです。
また、部活動という集団の中で感じた孤独や違和感も、小林さんにとっては大切な材料だったのではないでしょうか。
「自分は本当にここにいていいのか」といった問いが湧いてくるのも、感受性が強い人に多く見られる傾向です。
そうした感覚を持ちながらも、合唱という形でそれを昇華し、外に放つことができたことが、後の表現者としての軸に繋がっていったのだと感じます。
感情と向き合い、それを声にして放つ。
この中学時代の積み重ねが、小林直己さんの「内面から滲み出る表現力」の根っこにある気がしてなりません。
高校時代の葛藤と成長の記録


千葉県内でも有数の進学校に通いながら、部活動やアルバイト、将来への迷いと向き合っていた高校時代。
小林直己さんの原点とも言えるこの時期には、後の人生を大きく動かす転機や経験がいくつも重なっていました。
迷いながらも歩んだ日々のなかで、何を感じ、どう成長していったのか。
その足跡を辿ることで、小林さんの人間性がより深く見えてきます。
偏差値67の進学校・船橋東高校に一般受験で入学
小林直己さんが進学したのは、千葉県立船橋東高校。
1972年創立の県立校で、偏差値は67とかなり高く、地元でも知られる進学校のひとつです。
一般受験で入学していることからも分かるように、小林さんはもともと勉強にも真摯に取り組むタイプだったのでしょう。
この学校は勉学だけでなく部活動も盛んな校風で、文武両道の環境が整っていることが特徴です。
進学校というプレッシャーのなかで、自分の可能性を模索しながら日々を送っていたことが想像できますよね。
そんな中でも、小林さんは「周囲と同じ方向だけを目指すこと」に違和感を抱き始めていたようなんです。
成績や進路を気にする周囲の空気のなかで、自分の感性や情熱がどこに向かっているのか。
その問いに向き合う時間が、すでにこの頃から始まっていたのかもしれません。



私はここまで勉学に打ち込んできた経験はありませんが、周りとまったく同じことをしていくことに疑問を持つ気持ちわ分かる気がします。
合唱部とバスケ部の両立、そして新聞配達
高校時代の小林さんは、合唱部とバスケットボール部の二つの部活を掛け持ちしていました。
体育会系と文化系という異なるジャンルを両立していたのは、なかなか珍しいことですよね。
それだけ彼の関心が広く、また体力的にも精神的にもタフだったことがうかがえます。
さらに驚くのは、部活動に加えて新聞配達のアルバイトもしていたという点です。
配達先のマンションの階段を駆け上がり、早朝の冷たい空気の中で街を歩く。
その時間が、むしろ自分自身と向き合う貴重な時間だったと小林さんは語っています。
「お金がほしい」というシンプルな理由で始めたアルバイトも、やがて自分の将来や人生を考えるきっかけになっていったそうです。
静かな朝の空に広がる朝焼けを屋上から眺めながら、何を思っていたのでしょうか。
こうした日常の中にある気づきこそが、小林さんの感性を育てたのかもしれませんね。
渋谷通いと兄の助言がもたらした転機
高校生活のなかで、小林さんには約半年ほど、学校に行かなくなってしまった時期がありました。
その理由は明確には語られていませんが、音楽や表現の道に惹かれ、「シンガーソングライターになりたい」と思い始めていた頃だそうです。
その夢を追いかけたい気持ちと、現実の学校生活との間で揺れていたのでしょうね。
そんな時、兄からかけられた一言が転機となりました。
「とにかく家にいるな。渋谷に行け」
なぜ渋谷だったのか、小林さん自身も当時は分からなかったそうですが、兄の言葉には逆らえなかったと笑って話しています。
毎日渋谷に通い始めたことで、それまで高校生活が世界のすべてだったという考えが崩れ、新しい視点を得られたといいます。
街の雑踏の中で、さまざまな価値観に触れ、今まで知らなかった世界を見たことで、小林さんの中に新たな意識が芽生えていったようです。
この経験が、後に「表現者」としての道を本格的に歩み出す大きな一歩になったことは間違いありません。



家族からの言葉は本当に心に響きますよね!
ダンスとの出会いと高校復帰への決意
迷いの中で見つけたのが「ダンス」という表現手段でした。
17歳の頃、リズム感を身につけるために始めたダンスレッスン。
最初は身体を動かすことそのものが目的だったそうですが、次第にその魅力に引き込まれていきました。
言葉にできない感情を身体で表現できることに、解放感を覚えたと話しています。
このダンスとの出会いが、小林さんにとって大きな転機になったことは明らかです。
心の奥に溜まっていたエネルギーを形にできたことで、自分らしさを再発見できたのかもしれません。
その後、小林さんは母親の「シンガーソングライターになりたいなら、一般の高校生の気持ちも分かっておいたほうがいい」という言葉を受けて、高校へ復帰します。
そして、ダンスと学業を両立しながら、自分自身の歩むべき道を定めていきました。
迷い、立ち止まり、再び歩き出す。
その繰り返しのなかで見つけた「自分の足で立つ」という覚悟が、今の小林直己さんを形づくっているのでしょうね。
小林直己の大学生活と中退の真相
進学校を経て、法政大学文学部哲学科へと進んだ小林直己さん。その選択には確かな知的好奇心と人生に対する探究心が見え隠れします。
しかし、その大学生活は「卒業」ではなく「中退」という選択へと繋がっていきます。
華やかなダンサーの道と、思索の道を行き来しながら、小林さんがどんな想いで学生時代を歩んだのか、その足跡をたどってみましょう。
法政大学文学部哲学科を選んだ理由
小林直己さんが進学したのは、法政大学文学部哲学科。
偏差値は58ほどで、全国でも中堅以上のレベルに位置する学部です。
選んだ理由としては、高校時代に受けた倫理の授業がとても印象的だったからだそうです。
その中でも「愛とは何か」といったテーマに触れたときに、もっと深く学びたいと思ったことがきっかけだったと語っています。
ダンスや音楽といった表現の世界に身を置きながらも、「なぜ人は愛を求めるのか」「人間とは何者なのか」といった問いに心を奪われる。
その感性こそが、小林さんの独特な世界観の根源になっているのではないでしょうか。
哲学科という選択は、感情や思考を言葉にするトレーニングでもあり、アーティストとしての土台を築く場でもあったように感じます。
机に向かって思索を深める日々は、ダンスとは真逆のようでいて、実はどこか共通しているんですよね。
どちらも、自分の内面と向き合い、問い続ける営みなんです。
大学生活で得たものと中退を決断した背景
大学に入ってからの小林さんは、必ずしも「学生生活を満喫した」とは言えないかもしれません。
というのも、心の奥ではずっと
「ダンスを仕事にしたい」
「自分を表現する道に進みたい」
という願望があったからです。
しかしそれでも法政大学に進んだのは、すぐに夢へと飛び込むより、一度立ち止まり、自分の輪郭を見つけたかったからなのかもしれません。
実際に大学では哲学を学ぶ中で、「自分は何を考えて生きているのか」「どんな人間になりたいのか」といった根本的な問いに触れたといいます。
その過程で、小林さん自身が「愛について深く学びたいと思っていたが、実は“大人になるための時間”を求めていた」と気づいたエピソードも印象的です。
言葉にするのは簡単ですが、こうした内省ができるのは、相当成熟した感性の持ち主ですよね。
そして大学3年生のとき、ついにダンサーとして生きる決意を固めます。
ご両親に相談したところ、返ってきた言葉が「親はいつまでもそばにいるわけではない。自分で食べていく方法を見つけなさい」というものでした。
この言葉をきっかけに、小林さんは中退を選び、ダンスの世界に飛び込みます。
親の背中を見て育ってきた小林さんにとって、その一言は十分すぎるほどの後押しだったのでしょうね。
まとめ
- 学歴は、小林直己さんの表現力や人間性を理解するための重要な手がかり
- 哲学とダンス、異なる道が交差しながら彼の内面を深めていった
- 幼少期から大学時代までの一貫した「探求の姿勢」が今の表現者としての厚みを生んでいる
小林直己さんの歩みをたどると、学歴という言葉がただの経歴を超え、「自分を探す旅」だったことが伝わってきます。
哲学に心を動かされ、新聞配達で未来を考え、渋谷の雑踏で視野を広げ、ダンスで感情を解き放つ。
その一つひとつが、現在の静かな存在感と力強い表現に繋がっているんですよね。
ただ学びを得るのではなく、それをどう生かすかを自分に問い続けてきた姿勢が、今の小林さんの芯の強さを形づくっているように思えます。
これからも小林直己さんを応援していきたいと思います。